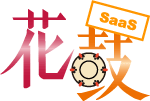参照文献:2007日本全体構造法臨床研究会全国大会講習会資料、道関 京子
失語症言語訓練支援サービス【花鼓SaaS】(はなつづみ サース)
トップページ > 失語症について
参考文献
- 米本恭三監修 道関京子編 新版 失語症のリハビリテーション 全体構造法 基本編 医歯薬出版 2016
- 米本恭三監修 道関京子編 新版 失語症のリハビリテーション 全体構造法 応用編 医歯薬出版 2016
- 道関京子編 全体構造法でとり組む 失語症の在宅リハビリ 医歯薬出版 2007
- 米本恭三監修 道関京子編 失語症のリハビリテーション-全体構造法のすべて 医歯薬出版 1997
- 米本恭三監修 道関京子編 失語症のリハビリテーション-全体構造法のすべて 第2版 医歯薬出版 1997
- 道関 京子 各症候に対するリハビリテーションの実際失語症「Monthly Book Medical Rehabilitation」 特集:高次脳機能障害リハビリテーション実践マニュアル pp.102-110 No70 2006/9 全日本病院出版
- 道関 京子 全体構造法(JIST法)による失語症訓練「高次脳機能障害-その概念と画像診断」 pp.51-59 中外医学社
- 道関 京子、金山 節子、安保 雅博、宮野 佐年 リハビリテーション技術 全体構造法 「Journal of Clinical Rehabilitation」 pp.362-364 Vol.13 No.4 2004/4
- 道関 京子 失語症患者と接するために(1) 「難病と在宅ケア」 Vol.6 No.5 pp.23-26 2000
- 道関 京子 失語症患者と接するために(2) 「難病と在宅ケア」 Vol.6 No.6 pp.51-54 2000
- 道関 京子 ヴェルボトナル法の用語 in 「ヴェルボトナル法入門」改訂版.第三書房 pp159-171 1999
- クロード・ロベルジュ監修、道関 京子編 「失語症の治療 -JIST(全体構造)法-」 ヴェルボトナル実践シリーズ3 1997 第三書房
- 道関 京子 失語症のタイプ診断とJIST法 第10回JIST全国研究大会 プログラム・抄録集 pp.10-21 2007
- 道関 京子 構造的失語症タイプ分類と全体構造(JIST)訓練―第1章タイプ分類― Vol.10 pp.3-11 2008 臨床言語研究 JIST journal
- Barlow,W.The Alexander technique.A.M.Heath and Company,Ltd,1973.(伊藤博訳.アレクサンダー・テクニック.誠信書房,1992)
- Bekesy,G.v.Can we feel the nervous discharges of the end organs during vibratory stimulation of the skin? J.Acoust.Soc.Am.34,6,850-856(1962).
- 深田英朗.口のストレッチング.ごま書房,1990.
- Franklin,B.The effect on consonant discrimination of combining a low-frequency passband in one ear and a high-frequency passband in the other ear.J.Aud.Res.9,365-379(1969).
- Franklin,B.The effect of combining low-and high-frequency passbands on consonant recognition in the hearing impaired.J.Speech Hear.Res.18,719-727(1976).
- Franklin,B.A comparison of the effect on con-sonant discrimination of combining low-and high-frequency passbands in normal,congenital,and adventitious hearing-impaired subjects.J.Am.Audiol.Soc.5,3,168-176(1979).
- Gelb,M.Body lerning - An Introduction to the Alexander technique -.Henry Hdt and Company,Inc,1987.
- Guberina,P.Phonetic rhythms in the Verbo-Tonal system.Rev.Phonet.Appl.16,3-13(1970).
- Guberina,P.Case studies in the use of restricted bands of frequencies in auditory rehabilitation of deaf. Zagreb,Project OVR-YUGO2-63,Institute of Phonetics,Faculty of Arts.1972,p.31.
- Guberina,P.The role of the body in learning foreign languages.Rev.Phonet.Appl.n,73-74-75,45(1985).
- 市川浩.精神としての身体. 勁草書房,1987.
- 鎌田勇.“意味と行為”現象学的社会学の展開.西原和久(編).青土社,1991.
- Keen,E.A Primer in Phenomenological Psychology.Holt,Rinehart and Winston,Inc,1975.(吉田章宏・宮崎清孝.現象学的心理学,第2版.東京大学出版会,1992).
- Левитин,К. Личностъю не рождаются.Издатедъстъо Прогресс,1983.(柴田義松監訳,ヴィゴッキー学派,ナウカ,1984).
- Леонтъев,А.Н. Проблемы развитияпсихики. второе издание, Изд,Мыслъ,1965.(松野豊・木村正一訳.認識の心理学.世界書院,1978)
- Liberman,A.M.Some results of research on speech perception.J.Acoust.Soc.Amer.29,117-123(1957).
- Linden,A.Distorted speech and binaural speech resynthesis tests.Acta Oto-Laryngol.v.58,32(1964)
- Mach,E.“Contour and Contrast Perception”.Sensation and Perception : an Integrated Approach,Schiffman H.R.(Ed.)New York,John Wiley & Sons,INC,1976,p.230-233.
- Martinov,N.Phonetic rhythms used for the stimulation and correction of speech in the Verbo tonal method.Studies on the Verbo-tonal System.Asp,C.W.(ed)Knoxville,University of Tennessee,1971,p.3-4.
- Merleau-Ponty,M.Phenomenologie de la perception,Gallimard,1945.(竹内芳郎・小木貞孝・木田元ほか訳,知覚の現象学1,みすず書房,1967)
- NHK編.日本語発音アクセント辞典.日本放送協会,1985.
- Palva,S.A.Filtered Speech Audiometory.Acta Oto-Laryngol.Supplementum 210.3-86(1965).
- Plummer,S.A.The effects of twenty-two conditions of band-pass filtering on three types of verbal material.Columbus,Ohio State University PhD Dissertation,1972.
- Roberge,C.不連続についての考察.言調聴覚研究シリーズ12,上智大学聴覚言語障害研究センター,1988.
- 田代晃二.美しい日本語の発音.創元社,1984.
- Ticinovic,I. & Sonic,L.Importance of Discontinuity in Frequency and Intensity during the Perception of Speech. Symposia Otorhinolaryngologica Jugoslavica,n.4,318-326(1971)(北村亜矢子訳.不連続についての考察.言調聴覚研究シリーズ12.東京,上智大学聴覚言語障害研究センター,1988,p.30-44).
- Vygotski,L.S.Thought and speech.Selected Psychological Studies.Academy of Pedagogical Science of the RSFSR,1958.(柴田義松,思考と言語,上下巻.明治図書,1980)
- 渡辺実.国語構文論.塙書房,1971.
- 渡辺実.国語文法論.笠間書院,1986.
- 山鳥重.神経心理学入門.医学書院,1986.
- 吉田角太郎,リズム教育の本質とその実際.奈良県立盲唖学校,1955.
- 吉田角太郎,リズムを基調とした音声言語教育の要訣.奈良県立盲唖学校,1956.